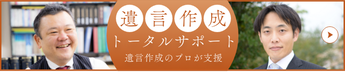高齢者虐待・障害者虐待に関する法律

専門職後見人として高齢者や障害者の人権保障に関与する「司法書士」としては、これらの方々に対する「虐待」を看過することはできません。
この記事では、高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法の概要について、解説しています。
| もくじ | |
|
〔凡例〕
この記事では、次のとおり略記します。
- 高齢者虐待防止法:高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
- 障害者虐待防止法:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
法律上の定義
高齢者虐待と、障害者虐待については、それぞれ別の法律で規定されています。
| 高齢者 | 障害者 | |
| 法律 | 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 | 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 |
| 被害者 | 65歳以上【1】 | 障害者【6】 |
| 加害者 |
|
【7】 |
| 態様 |
|
|
| 罰則 | 虐待をした者にペナルティを課すための法律ではない。 | 虐待をした者にペナルティを課すための法律ではない。 |
【1】65歳未満でも養介護事業サービスの提供を受ける障害者は、高齢者とみなして、養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する規定を適用する(法2Ⅵ)。
【2】養護者とは「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」
金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅の鍵の管理など、何らかの世話をしている者
(高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等)が該当し、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人等が養護者に該当する場合がある。
【3】養介護施設従事者等とは、老人福祉法又は介護保険法に規定する事業に限定。
しかし「現に養護」する者なら、養護者による虐待となる場合も
【4】経済的虐待の加害者には、養護者だけでなく「高齢者の親族」も含まれている
【5】本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること(一般社団法人日本福祉士会)。
<具体例>
- 日常生活に必要な金銭を渡さない。使わせない。
- 本人の自宅等を本人に無断で売却する。
- 年金や預貯金を無断で使用する。
- 入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を支払わない。
【6】「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう(障害者基本法2①)。
「社会的障壁」とは、障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう(障害者基本法2②)。
障害者手帳の有無や、難病の有無は、関係がない。
【7】学校、保育所、医療機関については、障害者虐待防止法29~31条を参照。
【8】身体的虐待に「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」が明示されてる。
身体拘束の「正当な理由」とは、以下の三要件の全てを満たすこと(*NPO法人PandA-J平成22年度障害者総合福祉推進事業費補助金事業「サービス提供事業所における虐待防止指針および身体拘束対応指針に関する検討」)
- 切迫性:利用者本人または他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合
- 非代替性:身体拘束以外に代替する対応方法がないこと
- 一時性:身体拘束は一時的なものであること
<身体拘束実施する際の注意点>
- これらの判断は施設全体で行ない、職員個人やチームで判断しないこと。
- 本人はもちろん家族などに十分な説明を行い同意を得ること。
- 目的・方法・時間・期間などを明示して、そのことを記録すること。
【9】ネグレクト「施設」と「使用者」については、施設利用者同士、職場の同僚同士による身体的、性的、心理的虐待を、施設・使用者が防止しないことも、虐待になる。
施設内、職場内のいじめ防止措置も求められる。
【10】心理的虐待について、施設と使用者に限り「不当な差別的言動」という例示。
【11】本人の合意なしに財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること(「虐待から考える成年後見人の役割」講義/高森裕司弁護士/240521)。
<具体例>
- 年金や賃金を渡さない。
- 本人の同意なしに財産や預貯金を処分、運用する。
- 日常生活に必要な金銭を渡さない。使わせない。
- 本人の同意なしに年金等を管理して渡さない。
法律の位置づけと考え方
2つの虐待防止法は・・・
- 行為者を処罰するためではない。
- 民事責任を追及するためではない。
- 虐待者の故意・過失、意図も問わない。
- 被虐待者の自覚も問わない。
法律は、すべての虐待を網羅するものではない
法律が対象としていない虐待を放置してよいということではない。
虐待防止の仕組み(スキーム)
早期発見
虐待の発見義務は、国と自治体の障害者関係機関にある(障害者虐待防止法6)。
cf. 高齢者虐待防止法には明文なし
民間の協力義務
| 義務を負う民間 | 義務の詳細 |
|
|
通報
通報義務者
虐待を受けたと思われる高齢者・障害者を発見した者全員に対して、義務が課されている。
>「思われる」とは、証拠を要さないという趣旨。
通報と守秘義務との関係
施設内虐待は、「虚偽」や「過失」が免責されない可能性がある。
上記をまとめると次のとおりです。
| 高齢者 | 障害者 |
|
|
|
|
|
上記をまとめると次のとおりです。
被害者が高齢者の場合
生命又は身体に重大な危険が生じている場合には通報義務。それ以外は通報努力義務(要介護施設従事者等は常に通報義務を負っている。)
被害者が障害者の場合
通報義務は「生命身体に重大な危険のおそれがある」かどうかで、通報義務と努力義務にわけず、一律に通報義務を何人にも課している。