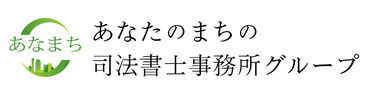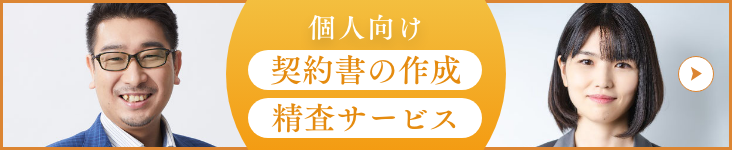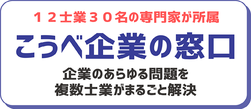- トラブル解決総論
- 相続・遺産分割トラブル解決
- 夫婦子供のトラブル解決
- その他親族トラブル解決
- 企業・事業者のトラブル解決
- 不動産・借地借家・隣近所のトラブル解決
- 不動産の取得時効と登記の関係
- 不動産賃貸借における関西方式・関東方式
- 敷金・保証金・建設協力金の違い
- 賃貸借契約の当事者が変更した場合、誰が誰に敷金を返せば良いか?
- 敷引特約の有効性
- 賃貸借契約で「中途解約を禁止する条項」は有効か?
- 賃貸借契約における更新料条項の有効性、更新料不払いの効果、法定更新との関係ほか後日もめないための具体的な対策
- 賃貸借契約で遅延損害金を年14.6%とする条項は有効か?
- 明渡しが遅れたときに賃料倍額の使用損害金を請求する条項は有効か?
- 借主の軽微な契約違反だけでは解除できない賃貸借契約「信頼関係破壊の法理」
- 家賃滞納による建物明渡請求
- 滞納賃料(家賃・地代)の請求を受けた連帯保証人の対応
- 賃借人が連帯保証人を立てない場合、賃貸人は賃貸借契約を解除できるか?!
- 借地に関する契約
- 借地権登記できない場合の「借地上の建物登記」民法177条の例外
- 建物賃貸借の契約期間を設定するときの注意点
- 借地上の建物を賃貸借するときの注意点
- DIY型賃貸借契約のメリットと注意点
- 原状回復・敷金返還に関するトラブル解決
- マンションの滞納管理費・修繕費・積立金の回収
- マンション義務違反者への対応
- 連棟建物(長屋、二戸一、三戸一)の切り離しトラブル
- マンション上階や二戸一の隣家からの水漏れトラブル解決
- 隣近所とのトラブル解決
- 隣地の建築計画はどこで確認するか?!宅地開発から建物建築までの流れ
- 建物建築に際しての周辺住民への説明義務
- 隣地が境界ギリギリに建築するのを止められませんか?!
- 崖地の擁壁・石垣の補修に関するトラブル【図解】
- 境界トラブル(筆界と所有権界)
- 私道の通行権をめぐるトラブル
- (ケガの後遺症や精神疾患などが原因で)騒音、大声、奇行などの問題行動をおこし周囲に迷惑をかけている方への対応(グループ会員限定記事)
- 交通事故解決
- 消費者トラブルの解決
- 借金が返済できないときの個人の債務整理(任意整理・民事再生・自己破産)
- 判決が出ても従わない相手方への強制執行による債権回収(差押え)
- 仮差押・仮処分など保全処分
- 刑事事件(被害者・加害者)
- 少年事件(被害者・加害者)
不動産賃貸借契約の当事者が変更した場合、誰が誰に敷金を返せば良いのか?

土地や建物の賃貸借契約も長期間になると当事者が変わることは良くあります。
そして、ここに敷金が絡んでくると、割とややこしいです。
場合分けをして考えてみましょう。
| もくじ | |
|
賃貸借契約の当事者に変更が生じる場合とは
整理すると、次のようになります。
賃貸人側(貸している地主・家主)の変動
| 賃貸人が自然人の場合 |
|
|
| 賃貸人が会社法人の場合 |
|
|
| || | || | |
| 特定承継❶ | 包括承継❷ |
賃借人側(借りている入居者・店子)の変動
| 賃借人が自然人の場合 |
|
|
| 賃借人が会社法人の場合 |
|
|
| || | || | |
| 特定承継❸ | 包括承継❹ |
当事者の変更があった場合の敷金返還請求権
上で分類したように
賃貸人に❶特定承継があったケース、❷包括承継があったケース
賃借人に❸特定承継があったケース、❹包括承継があったケース
に分けて考える必要があります。
❶賃貸人に特定承継(所有権の譲渡)があった場合
不動産を購入した買主は、賃貸人の地位も当然承継するか?
改正民法では、賃貸人の地位について、次のように定めています。
|
原 則 |
買主に移転する。 |
|
例 外 |
売主と買主が「①賃貸人の地位の売主への留保する旨と、②買主が売主へ賃貸する旨」を合意すれば、買主に移転しない(改正民法605の2)。 |
売主 → 賃借人
▼【原則】本来なら
買主 → 賃借人
▼【例外】合意で
買主 → 売主 → 賃借人
賃貸人の地位を承継した買主は、敷金返還債務を承継するか?
最高裁は「自己の所有建物を他に賃貸して引き渡した者が右建物を第三者に譲渡して所有権を移転した場合には、特段の事情のない限り、賃貸人の地位もこれに伴って当然に右第三者に移転し、賃借人から交付されていた敷金に関する権利義務関係も右第三者に承継されると解すべき」としています(最高裁39年8月28日判決(昭35(オ)596・民集18巻7号1354頁)、最高裁44年7月17日判決(昭43(オ)483・民集23巻8号1610頁)、最高裁平成11年3月25日判決(平7(オ)1705・集民192号607頁))。
改正民法では、賃貸人の地位とともに敷金返還債務は新賃貸人に移転する(改正民法605の2Ⅳ)としています。
❷賃貸人に包括承継(相続や合併)があった場合
不動産を相続した相続人は、賃貸人の地位も当然相続するのか?
賃貸人の死亡は、賃貸借契約の終了事由とされていませんので、不動産を相続した相続人は、当該不動産に関して締結されている賃貸借契約の賃貸人の地位を当然に承継します。
賃貸人の地位を相続した相続人は、単独で敷金返還債務を負担するのか?
敷金返還債務の相続については、次の二つの考え方が成り立ちます。
①敷金返還債務は可分債務であるため、法定相続分で当然分割される。
②賃貸人の地位と密接不可分であるため、賃貸人の地位を承継した相続人が当然全額を承継する。
大阪高裁令和元年12月26日判決(令元(ネ)1932、敷金返還請求控訴事件)は「敷金は,賃貸人が賃貸借契約に基づき賃借人に対して取得する債権を担保するものであるから,敷金に関する法律関係は賃貸借契約と密接に関係し,賃貸借契約に随伴すべきものと解されることに加え,賃借人が旧賃貸人から敷金の返還を受けた上で新賃貸人に改めて敷金を差し入れる労と,旧賃貸人の無資力の危険から賃借人を保護すべき必要性とに鑑みれば,賃貸人たる地位に承継があった場合には,敷金に関する法律関係は新賃貸人に当然に承継されるものと解すべきである。そして,上記のような敷金の担保としての性質や賃借人保護の必要性は,賃貸人たる地位の承継が,賃貸物件の売買等による特定承継の場合と,相続による包括承継の場合とで何ら変わるものではないから,賃貸借契約と敷金に関する法律関係に係る上記の法理は,包括承継の場合にも当然に妥当するものというべきである。」と述べ、相続による所有権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があった場合、敷金返還債務は新賃貸人が承継する(上の二つの考え方のうち②)としました。
❸賃借権が特定承継(賃借権譲渡)された場合
賃借権が有効に譲渡された場合【1】、賃貸人は旧賃借人に敷金を返還しなければなりません(民622の2Ⅰ②)ので、賃貸人としては新賃借人から新たに敷金を受領する必要があります。
したがって、賃借権が譲渡された場合には、敷金返還請求権は移転しない(最判S53.12.22民集32.9.1768)。
【1】賃借権を有効に譲渡できるのは次の2パターンのいずれかです。
- 賃借権の譲渡が契約で認められている場合
- 賃貸人の承諾を得た場合(改正民法612Ⅰ)
❹賃借権が包括承継(相続や合併)された場合
賃借権は相続の対象です。
賃貸人の承諾も必要とされていません。
敷金返還請求権も賃借権を相続した相続人が取得します。
関連する論点
賃料不払がある状態で所有権が譲渡された場合、敷金返還債務は?
賃料不払いが生じている状態で賃貸借不動産の所有権が譲渡(売買)された場合には、敷金返還債務はどうなるのでしょうか?次の二つの考え方ができると思います。
①賃料不払い分を敷金から充当した残額が新所有者に移転するのか
②敷金全額の返還債務が移転するのか
これについては、最高裁昭和44年7月17日判決(民集23.8.1610)は「旧賃貸人に差し入れられた敷金は、未払賃料債務があればこれに当然充当され、残額についてその権利義務関係が新賃貸人に承継される。」としています。
一方で、改正民法には規定がありません。
不動産売買契約書には、余計な紛争を生じさせないように、明記しておく必要があります。
人気の関連ページ
- 不動産賃貸借トラブル
-
- 不動産賃貸借における関西方式・関東法式
- 敷金・保証金・建設協力金の違い
- 権利金・礼金とは
- 賃貸借契約の当事者が変更した場合、誰が誰に敷金を返せば良いか?
- 敷引特約の有効性
- 賃貸借契約で「中途解約を禁止する条項」は有効か?
- 賃貸借契約における更新料条項の有効性、更新料不払いの効果、法定更新との関係ほか後日もめないための具体的な対策
- 賃貸借契約における遅延損害金14.6%の定め、使用損害金を賃料倍額とする定めは有効か
- 借主の債務不履行だけでは解除できない賃貸借契約(信頼関係破壊の法理)
- 家賃滞納による建物明渡請求
- 借主が滞納した賃料の支払請求を受けた連帯保証人の対応
- 無断譲渡・無断転貸による明渡請求
- 賃借人が連帯保証人を立てない場合、賃貸人は賃貸借契約を解除できるか?!
- 借地に関する契約
- 借地上の建物を賃貸借するときに注意すべき事項
- 短期賃貸借保護制度から明渡猶予制度へ
- 借家に関する契約
- 居抜き物件を借りたときのトラブル
- 原状回復に関するトラブル