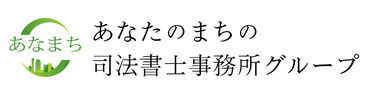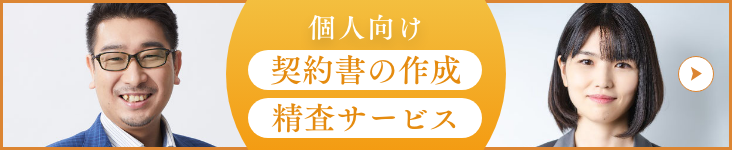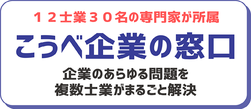- トラブル解決総論
- 相続・遺産分割トラブル解決
- 夫婦子供のトラブル解決
- その他親族トラブル解決
- 企業・事業者のトラブル解決
- 不動産・借地借家・隣近所のトラブル解決
- 不動産の取得時効と登記の関係
- 不動産賃貸借における関西方式・関東方式
- 敷金・保証金・建設協力金の違い
- 賃貸借契約の当事者が変更した場合、誰が誰に敷金を返せば良いか?
- 敷引特約の有効性
- 賃貸借契約で「中途解約を禁止する条項」は有効か?
- 賃貸借契約における更新料条項の有効性、更新料不払いの効果、法定更新との関係ほか後日もめないための具体的な対策
- 賃貸借契約で遅延損害金を年14.6%とする条項は有効か?
- 明渡しが遅れたときに賃料倍額の使用損害金を請求する条項は有効か?
- 借主の軽微な契約違反だけでは解除できない賃貸借契約「信頼関係破壊の法理」
- 家賃滞納による建物明渡請求
- 滞納賃料(家賃・地代)の請求を受けた連帯保証人の対応
- 賃借人が連帯保証人を立てない場合、賃貸人は賃貸借契約を解除できるか?!
- 借地に関する契約
- 借地権登記できない場合の「借地上の建物登記」民法177条の例外
- 建物賃貸借の契約期間を設定するときの注意点
- 借地上の建物を賃貸借するときの注意点
- DIY型賃貸借契約のメリットと注意点
- 原状回復・敷金返還に関するトラブル解決
- マンションの滞納管理費・修繕費・積立金の回収
- マンション義務違反者への対応
- 連棟建物(長屋、二戸一、三戸一)の切り離しトラブル
- マンション上階や二戸一の隣家からの水漏れトラブル解決
- 隣近所とのトラブル解決
- 隣地の建築計画はどこで確認するか?!宅地開発から建物建築までの流れ
- 建物建築に際しての周辺住民への説明義務
- 隣地が境界ギリギリに建築するのを止められませんか?!
- 崖地の擁壁・石垣の補修に関するトラブル【図解】
- 境界トラブル(筆界と所有権界)
- 私道の通行権をめぐるトラブル
- (ケガの後遺症や精神疾患などが原因で)騒音、大声、奇行などの問題行動をおこし周囲に迷惑をかけている方への対応(グループ会員限定記事)
- 交通事故解決
- 消費者トラブルの解決
- 借金が返済できないときの個人の債務整理(任意整理・民事再生・自己破産)
- 判決が出ても従わない相手方への強制執行による債権回収(差押え)
- 仮差押・仮処分など保全処分
- 刑事事件(被害者・加害者)
- 少年事件(被害者・加害者)
不動産賃貸借契約で「中途解約を禁止する条項」は有効か?

不動産賃貸借契約に関するご相談には、次のような「中途解約」に関するものがあります。
- 賃貸借契約に「中途解約」について何も記載がない場合、賃借人は契約期間中には解約できないのでしょうか?!
- 「中途解約禁止にしたい」場合には、どうすれば良いのでしょうか?!
- 「中途解約によって損害が発生するのを予防したい」という場合には?!
このコラムでは、不動産賃貸借契約の「中途解約」に焦点を当てます。
| もくじ | |
|
法律の定め
中途解約の可否については、賃借人の立場から考えると分かりやすいと思います。
【設問】
次のような不動産賃貸借契約書がある場合、賃借人はいつでも中途解約できるでしょうか?
|
条文を見るとすぐに答えがわかります。
|
民法第618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保) 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
民法第617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
|

中途解約の原則と例外
上記民法の条文をまとめると下表のような原則と例外になっていることが分かります。
| 契約期間の定めあり | 原則 | 中途解約できない |
| 例外 |
中途解約できると契約したとき ☞中途解約できる(民618)。 |
|
| 契約期間の定めなし | いつでも解約できる(民617)。 | |
なんと設問の場合には、中途解約できないんですよね。
そうすると、賃貸人が中途解約されたくない場合には、わざわざ「中途解約禁止」と契約書に書く必要はなさそうにも思えますが・・・もう少しお付き合いください。
賃貸人だけをさらに縛る法律(借地借家法)
ついでに、賃貸人だけを縛る借地借家法の条文をご紹介しておきます。
借地借家法第27条(解約による建物賃貸借の終了)
借地借家法第28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。【1】
借地借家法第29条(建物賃貸借の期間)
借地借家法第30条(強行規定) この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効【1】とする。 |
【1】この解約に正当事由を要求している借地借家法28条、特約で借地借家法よりも賃借人に不利なものは無効とする借地借家法30条が、賃貸人を厳しく制限しています。
中途解約権を与える特約は有効か?
「賃借人」に中途解約権を与える特約
有効です。
なぜなら、中途解約条項を設けた場合、賃借人には賃貸借契約を終了させたいときに終了できるメリットがある賃借人の利益となる規定ですので借地借家法上の制約は存在しません。したがって、契約書どおりに中途解約ができることとなります。
「賃貸人」に中途解約権を与える特約
一応有効です。
その有効性につき争いがありましたが、解約権留保特約に基づく解約申入れの場合にも正当事由(借地借家法28)が必要ですから、必ずしも賃借人に不利にならないとして、特約の有効性を認めるのが通説です。
最高裁判例はありませんが、下級審の裁判例も同じ立場です(東京地判昭和55.2.12判時965号85 頁など)。
中途解約を禁止にしたい場合、契約書に記載しなくて良いか?!
二つの考え方
- 契約期間の記載のみがあり、中途解約に関する条項がない場合には、その期間は契約が継続し、中途解約できないのが原則ですので、わざわざ契約書に「中途解約禁止」と表現して悪目立ちし、賃借人に注目されるのを避けるのも一つの方法でしょう。
- もっとも「契約書に記載されていない事情を持ち出して、契約の意思解釈として中途解約が認められると主張されることも皆無ではないと思われるため、争いの芽を摘んでおくためにも、明確に中途解約禁止条項を規定しておくことが望ましい(阿部・井窪・片山法律事務所/編『契約書作成の実務と書式 -- 企業実務家視点の雛形とその解説』第2版(有斐閣、2021年)109頁)」ともいえます。
どちらを採用するかは、大家さん次第になります。
私個人的には、争いの芽は摘んでおいた方が良いと考えています。「数か月前に通知さえすれば、いつでも解約できる」と考えている賃借人が多いからです。
「中途解約禁止」としたい場合に、工夫できることはないでしょうか?
違約金条項はどうか?!
実務でも、一定期間必ず賃貸借契約を継続させたい場合には中途解約禁止条項を設けることが多いです。
ある賃借人に賃貸することを前提に、賃借人仕様にして建物を建設し賃貸する場合、「その」賃借人からの賃料で建設費などを賄う必要があります。「その」賃借人の要望に応じて建設した「その」建物には汎用性がないため、「その」賃借人が退去したら、次の賃借人を探すのは困難だからです。
こういう場合、短期間で賃貸借契約を解除されないためには、工夫が必要です。
阿部・井窪・片山法律事務所/編『契約書作成の実務と書式 -- 企業実務家視点の雛形とその解説』第2版(有斐閣、2021年)118頁
は、次の2つの方法を提案なさっています。
賃貸借期間は投下資本を回収できるだけの期間に設定した上で・・・
- 中途解約禁止条項を設けておく
- 中途解約は認めた上で、中途解約の場合には、契約期間満了までの賃料相当額を違約金として回収できる条項を定めておく
佐藤大輔の私見
上記書籍のご提案のうち特に2つ目には違和感を感じます。すなわち、中途解約という「権利」を認めながら、権利行使に「違約金」を必要とすることに関する違和感です。
それならいっそ「中途解約を禁止して」(違約として)、違約した場合に違約金の方が良いのではないでしょうか。
賃貸実務で多く採用されている方法
次の定め方は、実務でもよく見受けられる契約書対応ですが、一番無難かと思います。
賃貸借期間は投下資本を回収できるだけの期間に設定した上で・・・
- 「敷金」ではなく、あえて「保証金」という文言を使う。
- 中途解約の可否は、あえて記載しない。「記載してない場合には中途解約は禁止」となることは上記のとおりです。
- 契約期間途中の解約を行わなかった場合に、保証金が満額返ってくるという恩恵を与える。
契約書文言に落とし込むと次のとおりです。
| 第7条(保証金) | |||
|
|||
| 本契約締結から明渡しにいたるまでの期間 | 返還する保証金から控除すべき割合 | ||
| 5年未満のとき | 保証金の80% | ||
| 5年以上10年未満のとき | 保証金の60% | ||
| 10年以上15年未満のとき | 保証金の40% | ||
| 15年以上20年未満のとき | 保証金の20% | ||
| 20年以上のとき | 保証金の 0%(保証金全額を返還する。) | ||
| 7.前項ただし書の場合には、甲は、敷金から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなければならない。 | |||
賃貸借契約が賃借人から見て消費者契約にあたる場合の注意点
事業用の賃貸借の場合には問題ありませんが、居住用の賃貸借契約を一般消費者と締結する場合には違約金の定めには消費者契約法の適用がありますので、注意が必要です。
人気の関連ページ
- 不動産賃貸借トラブル
-
- 家賃滞納による建物明渡請求
- 借地に関する契約
- 借地上の建物を賃貸借するときに注意すべき事項
- 短期賃貸借保護制度から明渡猶予制度へ
- 借家に関する契約
- 不動産賃貸借における関西方式・関東方式
- 居抜き物件を借りたときのトラブル
- 原状回復に関するトラブル
- 敷引特約の有効性
- 賃貸借契約で「中途解約を禁止する条項」は有効か?
- 賃貸借契約における更新料条項の有効性、更新料不払いの効果、法定更新との関係ほか後日もめないための具体策
- 賃貸借契約における遅延損害金14.6%の定め、使用損害金を賃料倍額とする定めは有効か