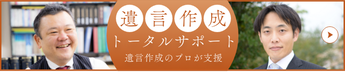相続回復請求権(民法第884条)は、いつ、どのように使うのか?!

相続権を侵害されたときには、相続回復請求を行うことができますが、実務上は、次のようになっています。
- △ 請求原因としては、あまり使われていません(つまり、普通は「相続権を侵害しているから、相続回復請求権に基づいて、金○円を支払え」や「相続権を侵害しているから、相続回復請求権に基づいて、○○不動産を引き渡せ」などとは使いません。)
- 〇 消滅時効の抗弁として、使われているケースが多いです(つまり「他の相続人によるこの請求は、相続回復請求権だから消滅時効にかかっている」というように使います。)。
| もくじ | |
|
民法884条
民法884条から分かること。分からないこと。
| 民法884条(相続回復請求権) | |
| 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。 | |
民法上、相続回復請求権について規定した条文はこの一条だけです。
相続回復請求権の行使期限を定めただけの条文、そして、たった一条しかない条文からは、
- 相続回復請求権の存在意義や内容、
- 行使するための要件、
- 物権的請求権との関係
は分かりません。
物権的請求権の存在から導かれる仮説
相続が開始すると、遺産は「相続人全員による準共有」となります。
ですから・・・
「他人」が遺産を占有している場合は、「共有持分権に基づき」妨害排除請求をすれば足ります。
「他の相続人」が遺産を占有している場合は、「共有持分権に基づき」遺産分割協議を求めれば良いのです。
これら妨害排除請求権や、遺産分割を求める権利は、所有権に基づく権利ですので「物権的請求権」といいます。
そして本来、物権的請求権は、消滅時効にかかりません。
本来、消滅時効にかからない権利を消滅時効により消滅させようというのが、民法884条の意義なのだと思われます。
現実にも、真正な相続人と表見相続人との争いではなく、共同相続人という真正な相続人同士の遺産分割の争いの中で、法定相続分の一部を侵害されている共同相続人が他の共同相続人に対して共有持分に基づく抹消登記請求や移転登記手続を求めた場合に、自己の法定相続分を超えて遺産を占有する者から相続回復請求権の時効消滅が主張するケースが多いのです。
判例のご紹介
最高裁大法廷昭和53年12月20日判決
|
共同相続人の一人甲が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分につき他の共同相続人乙の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分に属すると称してこれを占有管理し、乙の相続権を侵害しているため、乙が右侵害の排除を求める場合には、民法884条の適用があるが、甲においてその部分が乙の持分に属することを知つているとき、又はその部分につき甲に相続による持分があると信ぜられるべき合理的な事由がないときには、同条の適用が排除される。 (要旨は、Westlaw Japanによる。) |
実際に時効援用を認めた判例
| 最高裁第三小法廷昭和54年7月10日判決 | |
|
一 旧民法下の遺産相続による共同相続人の一人甲が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分について他の共同相続人乙の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分に属すると称してこれを占有管理し、乙の相続権を侵害しているため、乙が右侵害の排除を求める場合には、相続回復請求権の規定の適用があるが、甲においてその部分が乙の持分に属することを知つているとき、又はその部分につき甲に相続による持分があると信ぜられるべき合理的な事由がないときは、同規定の適用が排除される。
二 旧民法下の遺産相続による共同相続人の一人乙女が遺産分割前に他の共同相続人甲男を家督相続人に指定して隠居したが、右隠居時に乙に胎児がいたことにより右指定が無効であり、乙が遺産相続権を失わないため、甲において相続財産のうち乙の相続部分もまた右指定により自己に帰属したとして同部分に対し占有管理を続けたことが乙の遺産相続権に対する侵害となる場合においても、胎児が生後まもなく死亡したため、甲において右指定の無効を知りえず、かつ、その無効を知りえなかつたことが客観的にも無理からぬものであるときは、乙の甲に対する右侵害排除を求める請求について、相続回復請求権の規定の適用がある。 (要旨は、Westlaw Japanによる。) |
|
悪意有過失の相続人からの転得者(第三者)は、相続回復請求権の消滅時効を援用できない。
| 最高裁第三小法廷平成7年12月5日判決 | |
|
共同相続の場合において相続回復請求制度の問題として扱うかどうかを決する右のような悪意又は合理的事由の存否は、甲から相続財産を譲り受けた第三者がいるときであつても、甲について判断すべきであるから、相続財産である不動産について単独名義で相続の登記を経由した共同相続人の一人甲が、甲の本来の相続持分を超える部分が他の相続人に属することを知っていたか、又は右部分を含めて甲が単独相続をしたと信ずるにつき合理的な事由がないために、他の共同相続人に対して相続回復請求権の消滅時効を援用することができない場合には、甲から右不動産を譲り受けた第三者も右時効を援用することはできないというべきである。
(要旨は、Westlaw Japanによる。) |
|
|
乙の相続権を侵害し、乙に訴えられた 【甲の属性】 |
甲が、乙の請求を相続回復請求権であるとして その消滅時効を援用できるか否か |
| 悪意or有過失の「他の共同相続人」 | 援用不可(最高裁大法廷昭和53年12月20日判決) |
|
悪意or有過失の「他の共同相続人」から 譲渡を受けた転得者 |
援用不可(最高裁第三小法廷平成7年12月5日判決) |
| 善意&無過失の「他の共同相続人」 | 援用可能(最高裁第三小法廷昭和54年7月10日判決) |