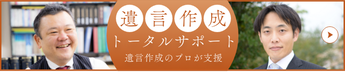法律文書作成のルール

このページは、当司法書士事務所グループに就職した新人向けに作成した説明書を、一般に公開したものです。
理解し易くするため、細かい例外などを省いて説明しています。
皆様のご参考になれば幸いです。
「Ctrl」+「F」で[検索]できます。
| もくじ | |
|
裁判所提出文書のフォーマット
| 余白 |
上35 下30
左30 右20 |
| 文字数 |
12ポイント
37文字/行 26行/頁 |
| 所内ルール |
通常文字は、12ポイント・MS明朝体 大きな見出しは、12ポイント・MSゴシック・太字 |
内容証明のフォーマット
| 文字数 |
20文字/行 26行/頁 |
| 所内ルール | 12ポイントの文字サイズとする。 |
見出し符号
|
公用文では、次のとおり用いられています。
第1. 1. ⑴ ①【1】 ア (ア) a (a)
【1】公用文に関する規程(昭和63年4月1日訓令第1号)では、①②は採用されていないが、民間では、分かりやすいので、よく使用される。 |
|
本文と「見出し符号」の位置関係は次のとおりとする(あなまち基準) □は余白、◎は文字をあらわす。
第1.◎◎<MS太ゴシック> □□◎◎◎◎(一行目) <MS明朝体> □◎◎◎◎◎(二行目以下) <MS明朝体> 1.◎◎<原則、MS明朝体。長文のときは、MS太ゴシック> □□□◎◎◎(一行目) <MS明朝体> □□◎◎◎◎(二行目以下) <MS明朝体> ⑴ ◎◎ □□□□◎◎(一行目) <MS明朝体> □□□◎◎◎(二行目以下) <MS明朝体> ① ◎◎ □□□□□◎◎(一行目) <MS明朝体> □□□□◎◎◎(二行目以下)<MS明朝体> <以下、同様> |
数字
|
原 則 |
数字は、算用数字を用いる |
|
例 外 |
次の場合には、漢字を用いる。 ア 「二重原」、「廿日市二丁目」などのように固有名詞に用いる場合 イ 「二、三日」、「数十日」などのように概数を示す場合 ウ 「一般」、「一部分」、「四捨五入」などのように数量的な意味が薄くなつた語に用いる場合 エ 「100万」、「10億」などのように万以上の数の単位として用いる場合 オ 「一つずつ」、「二間続き」などのように「ひとつ」、「ふたつ」などと読む場合 カ 「前二項」「前三項」などと契約書中に用いるとき |
|
例 外 |
縦書きの場合には、「一」、「二」、「三」、「十」、「百」、「千」、「万」、「億」等の漢字を用いるものとする。 |
数字の単位
- 文書の数は「部」を用いる。
(例)「6部」
(誤)「6通」はダメ - 人数は「人」を用いる。
(例)「3人」
(誤)「3名」はダメ
(日本司法書士会連合会「法律文書作成に関する研修会<第1回>」鮫川誠司弁護士/2025.2318/レジメ22頁)
かっこ(公用文に関する規程第8条)
| 種類 | 呼称 | 一般的な用い方 |
| ( ) | 括弧(かっこ) | |
| 〔 〕 | そでかっこ |
括弧内で、さらに括弧を用いるときに用いる。 ( 〔 〕 ) |
| 「 」 | かぎかっこ |
引用する語句 強調する語句 |
| 『 』 | 二重かぎかっこ |
カギ括弧内で、さらにカギ括弧を用いるときに用いる。 「 『 』 」 |
接続詞
|
原 則 |
接続詞全般 |
|
|
例 外 |
及び 並びに 又は 若しくは |
|
| 種類 | 一般的な用い方 |
| 及び【3】 |
A及びB A、B及びC A、B、C及びD |
| 並びに |
ABとCが違う種類のとき▶(A及びB)並びにC ABとCDが違う種類のとき▶(A及びB)並びに(C及びD) ABとCとDが違う種類のとき▶((A及びB)並びにC)並びにD ※()は使わない |
| 又は【3】 |
A又はB ※「又は」が使用されない場面に「若しくは」だけが単独で使用されることはない。 ※「また」は平仮名で書く。 |
| 若しくは |
(A若しくはB)又はC (A、B若しくはC)又は(C、D若しくはE) ※「又は」と「若しくは」は、「又は」の方が大きいくくりになる。 |
| あるいは | 契約書では使わない。 |
【1】平仮名で書くべき接続詞は次のとおり(及び、並びに、又は、若しくは以外のすべて)
| ○また | ×又(「又は」は漢字表記が正解) |
|
○したがって |
×従って |
| ○ただし |
×但し |
| ○ゆえに | ×故に |
| ○おって | ×追って |
| ○かつ | ×且つ |
【2】「ただし」「ただし書き」については誤用が多い。
| ○ただし、 | ×但し |
|
○ただし書き |
×但書 ×但し書き ×ただし書 |
【2】「又は」と「及び」を一つの文章中でどう使うか?どう解釈するか?
例えば・・・
| 会社が公告をする方法「官報又は東日本新聞及び熊本日日新聞」 |
とあったとき、どう解釈するのか?
➀「官報」又は「東日本新聞及び熊本日日新聞」と解釈するべきか?
②「官報又は東日本新聞」及び「熊本日日新聞」と解釈するべきか?
➀の解釈をとると、公告方法としては違法です(株主が、官報を見れば良いのか、それとも東日本新聞と熊本日日新聞のどれを見ればよいのか、分からないからです。)。
②の解釈をとると、公告方法として合法です(株主は、熊本日日新聞さえ見ていれば、会社の広告を見落とすことがないからです。)。
さて、「又は」と「及び」の関係性について説明している文献などを見つけることはできませんでした。しかし、法令中に使用例がありました。
| 会社法第27条(定款の記載又は記録事項) | |
|
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 ⑤ 発起人の氏名又は名称及び住所 |
|
この条文を見ると次のように解釈できます。
発起人の(発起人が個人のときには)氏名又は(発起人が法人や会社のときには)名称及び住所
▽
発起人の「氏名又は名称」及び「名称」
▽
解釈方法:「又は」と「及び」は、「又は」の方が前後の単語を結びつける力が強いと考えられる。
▽
使用方法:契約書などは誰が読んでも、誤解無く、一つの意味を指す必要があります。
「又は」と「及び」の一文中での使用は、文章を分かりにくくするので、避けるべきです。
【4】接続詞の直前における読点(、)の要否
- 名詞を並列して用いる場合:読点は不要。
(例)「A、B又はC」(Bと又はの間に読点は不要) - 動詞を並列して用いる場合:読点は必要。
(例)「・・・を変更し、又は取り消すことができる。」 - 名詞を並列して「その他」でくくる場合:読点は不要。
(例)「A、Bその他C」 - 動詞を並列して「その他」でくくる場合:読点は必要。
(例)「Aし、Bし、その他Cする。」 - 名詞を並列して「かつ」でくくる場合:読点は不要。
(例)「有用かつ適切」 - 動詞を並列して「かつ」でくくる場合:読点は必要。
(例)「整理し、かつ、分類する。」
注釈【4】につき、日本司法書士会連合会「法律文書作成に関する研修会<第1回>」鮫川誠司弁護士/2025.2318/レジメ16頁を参照。
接尾語、副助詞(など、等)
| 等、など |
法令用語としては「等」を使い、「など」と平仮名表記しない。 また「トウ」と読む。 |
補助動詞(いただきます。いたします。くださいますよう・・・)
| 動詞 | 補助動詞 |
| 漢字で書く |
平仮名で書く |
| お土産を頂きました。 |
参考にさせていただきました。 |
| 私の不徳の致すところ |
お願いいたします。 |
| 司法書士に言う。 |
司法書士という職 △△(以下「〇〇」という。) 〇〇(△△をいう。以下同じ) |
| お返事を下さい。 |
〇〇してくださいますようお願い・・・ |
| 名詞 | 動詞・副詞 |
| 漢字で書く |
平仮名で書く |
| 上出来・出来合 |
〇〇することができる。 |
か月、箇月
| か月 | 前に算用数字が来るとき(=横書きのとき)に使う。 |
| 箇月 | 前に漢数字が来るとき(=縦書きのとき)に使う。例)官報 |
| ケ月 | 使わない |
| カ月 | 使わない |
場合、とき、時
| 時 |
ある時間を瞬間的に捉えて押さえるときに使う。 例)株主から請求がある時までは(会社法215Ⅳ) |
| 場合 |
前提条件をあらわす。どちらを使っても良い。 前提条件を重ねて表現したい場合には、「場合」がより大きな条件を表し、「とき」はそれよりも小さな条件に使用する。 例)次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは(会社法247) |
| とき |
附、付
| 附 |
次の5語のみ「附」を使う。 附則、附属、附帯、附置(ふち)、寄附 |
| 付 |
上記以外は「付」を使う。 付随・・・(気になる場合には、e-GOV法令検索のTOP画面で単語を検索してみれば、附か付のどちらを使うべきか分かります。)
|
「附」について、(日本司法書士会連合会「法律文書作成に関する研修会<第1回>」鮫川誠司弁護士/2025.2318/レジメ15頁)
固有名詞のアルファベット表記(令和元年10月25日関係府省庁申合せ)
|
日本人姓名をローマ字表記する際 ・「姓ー名」の順に表記する。 ・姓と名を明確に区別させる必要がある場合には、姓を全て大文字とする。 ▼つまり ・佐藤大輔は、「SATO Daisuke」と表記する。 |
「ものとする」の誤用に注意
権利を表したい場合:○○できる。
義務を表したい場合:しなければならない。ものとする(※)。
禁止事項を表したい場合:してはならない。することができない。
(※)「ものとする」は、「しなければならない」を弱めたもので、義務を表す。
したがって、「できるものとする」との表現は誤用。権利か義務か不明になる。
こんなときには「できる」で止める。
(日本司法書士会連合会「法律文書作成に関する研修会<第1回>」鮫川誠司弁護士/2025.2318/レジメ19頁を参照)
「等(とう)」の誤用に注意
外延が不明確になるため、「等(とう)」を「+α」の意味で用いてはならない。
略称として用いるときは、必ず定義を置く。
(例)「A及びB(以下、これらを併せて「A等」という。)は、」
「その他」「その他の」の誤用に注意
- 「その他」は、前後の句が並列の関係のときに用いる。
(例)「A、Bその他C」 - 「その他の」は、前の句が後の区の例示の関係のときに用いる。
(例)「A、Bその他のC」
引用・参考・参照・出典
●「引用」とは
書籍や資料の文章(引用元)をそのままの状態で自分の書面に記載することです。
引用で重要なのは、引用元の文章を「そのまま記載すること」です。
●「参考」「参照」とは
「参考」とは書籍や資料の文章(参考元)を要約したものです。
「引用」では引用する元の文章を勝手に変更できませんが、「参考」では自分の言葉に置きかえてその内容をまとめて要約します。
参考とよく似た言葉に「参照」がありますが、言葉の意味は「参考」>「参照」です。「参考」を使いましょう。
●「出典」(しゅってん)とは
「引用」又は「参考」にした著作物そのもののことです。
| 「引用」や「参考」が著作権法違反にならないための要件(著作権法第32条)。 | |
|
⑴「出典」を明記すること ⑵すでに出版されている書物や、インターネットで公開されている記事であること ☛未公開のものを引用・参考は出来ません。 ⑶自分の意見を書いた文章と明確に区別すること ⑷質量ともに、自分の文書が「主」で、引用した部分が「従」であること ⑸引用する必然性があること |
●出典の正しい記載方法
統一ルールは無いものの、同一の文書中では統一すること。
「書籍の場合」著者名・書名・編集者名・出版社・出版年・該当頁
「雑誌の場合」著者名・記事タイトル・雑誌名・号数・発行年月・該当頁
「ウェブサイトの場合」著者名・ウェブページのタイトル・URL・最終アクセス年月日
●その他
細かい記載方法については、以下にならってください。