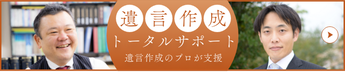- 起業支援(会社団体の設立運営支援)・スタートアップ支援
- 事業を始める皆様へ「プチ顧問サービス」のご紹介<月額1.1万円>
- 儲かるビジネス4つの原則
- 会社って何なんだろう?!商売を始めるなら、個人事業か会社かどちらが良いの?
- 少数株主側が取締役の地位を確保したいときに検討すべき「累積投票」制度
- 2人以上の出資で会社を設立するとき必要な「創業(者)株主間契約」
- スタートアップ(ベンチャー)の起業支援
- ベンチャー・スタートアップ用語辞典
- スタートアップの資本政策❶総論
- スタートアップの資本政策❷資本政策の作り方と投資の受入れ
- スタートアップの資本政策❸資金調達スキーム(普通株、優先株、みなし優先株、新株予約権、J-KISS)を徹底比較
- スタートアップの資本政策➍優先株の注意点
- スタートアップの資本政策❺投資契約
- スタートアップの資本政策➏投資契約と種類株式の違い
- スタートアップのエグジット(出口)戦略
- 投資を受け入れるとき必要な「株主間契約・株主間協定(SHA)」
- 自動車をレンタル・リースする会社の設立
- 獣医さんの会社設立(動物病院の法人化)
- 保育所・幼稚園・認定こども園を作りたい
- 会社設立登記を依頼すべき専門家・依頼してはいけない専門家
- 会社や法人が子会社を設立するとき(発起人が会社のとき)の注意点
- 子会社・関連会社設立~別会社設立のメリットと、別会社を設立する場合に①子会社にするべきか②社長出資で設立するべきか
- スーパー・ファストトラック・オプションによる会社設立
- 流行る(はやる)商号・屋号の付け方
- 類似商号・登録商標等の調査は必要か?!
- 設立する会社の本店は、どこに置けば良いの?バーチャルオフィスとかどうですか?
- 会社や法人の「事業目的」は、どうやって決めれば良いの?!
- 会社は「企業理念」を登記できますか?!
- 会社設立日はいつ(何月何日)が良いか?
- 会社設立の税金軽減(創業支援)
- 会社法人設立後の必要手続と、それぞれを担当する専門家士業
- 設立前後のお金の流れ・動かし方(株式会社・合同会社共通)
- 法人口座を設立登記申請中より申込可能(提携金融機関のご紹介)
- 借りたお金を資本金にする「見せ金」は違法!
- 会社設立の出資金の入金方法、通帳コピーの作成方法(出資払込証明)
- 会社名義の銀行口座が作れない理由と対処方法
- 設立時に作るべき印鑑の種類は?!注文の注意点やタイミングは?!
- 会社設立日に印鑑(ハンコ)が間に合わない!どうすれば?!
- 会社法人の印鑑届出について
- 株式会社の設立
- 合同会社(LLC)の設立
- 一般社団法人の設立
- 非営利型一般社団法人の設立
- 一般財団法人の設立
- 公益社団法人・公益財団法人の設立
- NPO法人(特定非営利活動法人)の設立
- 有限責任事業組合(LLP)の設立
- 有限責任事業組合(LLP)と事業協同組合の違い
- そもそも組合とは何か?
- 労働者協同組合の設立
- マンション管理組合法人の設立
- 税理士法人の設立
- 弁理士法人(旧・特許業務法人)の設立
- 司法書士による顧問契約のご紹介
- 従業員支援プログラム(EAP)
- 法務部門支援
- 内部統制システム(コーポレートガバナンス)構築支援
- 株主総会・取締役会など運営支援
- 組織再編(会社分割・合併・組織変更・株式移転など)
- 会社・法人の事業承継
- M&A・ジョイントベンチャー(合弁事業)
- 会社や法人の登記
- 医療法人その他医療機関の登記
- 企業・事業者の資産管理・運用
- 会社の再生・倒産(負債が大きい会社)
- 会社の通常解散(負債が少ない会社の休業・廃業・解散)
- セミナー講師
スタートアップのエグジット(出口)戦略

ベンチャー企業(スタートアップ)は、ビジネスが成功すれば大変儲かります。
また、投資家から集めた資金を何十倍、何百倍にもして、投資家にも儲けさせる必要があります。
「スタートアップのゴールはどうするのか?」これを『エグジット(出口)戦略』といいます。
この記事では、スタートアップのエグジット(出口)戦略について、解説しています。
| もくじ | |
|
目指すべき「二つの出口」
株式の上場(IPO、アイピーオー)
会社の株式を証券取引所に上場すると、自由に株式を売買することができるようになります。
投資家は、自分が買った値段よりも高く株式を売却することができれば儲けを得ることができます。
この株式売却益のことをキャピタルゲインといいます。
Buy-Out(バイアウト、買収される、M&Aされる)
株式を上場するのではなく、別の会社に買い取ってもらうことによっても創業者や投資家は儲けることができます。
株式市場の種類と選択
株式市場の種類
|
取引所の名称 |
トピックス/市場区分 |
|
東京証券取引所 略称:東証 よみ:とうしょう |
2013.1 大阪証券取引所が、東京証券取引所と経営統合し「東京証券取引所の大阪取引所」となる。 2022.4 旧市場区分(市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQ(スタンダード、グロース))を廃止し、新市場区分(下欄)に変更。 |
|
<新市場区分>
|
|
| TOKYO PRO Market |
東証とロンドン証券取引所の共同出資で設立された市場。 プロ投資家しか買えない。 |
|
名古屋証券取引所 略称:名証 よみ:めいしょう |
|
|
福岡証券取引所 略称:福証 よみ:ふくしょう |
|
|
札幌証券取引所 略称:札証 よみ:さっしょう |
|
スタートアップが最初に目指す市場
東証グロースに要求される「高い成長性」を説明できず
東証スタンダードに要求される「企業規模がない」場合
名証、福証、札証か、プロ投資家向けのTOKYO PRO Marketへの上場を検討する。
(IPO Forum編/経営者のためのIPOバイブル第2版/2022/8頁より)
何年で上場を目指すか
起業から何年ぐらいでの上場を目指せば良いのでしょうか?
その答えは、直近の上場企業の社歴を見ると明らかになります。
1990年代
かつては上場する企業は、会社設立から20年から30年の企業が多かったといわれています。
そのため投資家は上場直前のレイターステージで投資していました。
会社設立後のベンチャーに投資をして上場まで20から30年かかるということは、投資額を回収するまでに20から30年もかかってしまうことを意味するからです。
1999年以降
1999年、株式売買委託手数料の自由化をはじめとした「いわゆる証券自由化」が行なわれ、手数料の低額化を背景に、富裕層以外の個人投資家も株式売買を行なうようになりました。
1999年11月、主に「ベンチャー企業を対象」にした市場「東証マザーズ」が開設されました。
2000年6月、市場「ナスダックジャパン」が開設されました。
これらの投資家層の拡大、新興市場の開設により、上場のハードルが下がり、設立からの年数が短い企業が上場するようになりました。
設立から年数が短い企業が上場できるということは、シードやアーリーの時期に投資しても投資家は投下資本の回収にそれほど時間を要さないということになります。
その後、そして現在
1990年代に始まったITバブルが2001年に完全に弾け、その後の不祥事を受け、上場のハードルは上がっています。
しかしながら「設立から上場までの期間が短い絵を描けるベンチャーほど投資を受けられやすい」ことに変わりはありません。