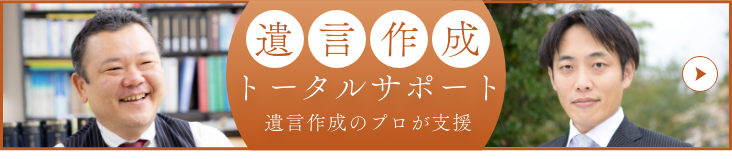- 不動産名義変更・不動産登記
- 終活TOP●終活とは?元気なうちに始める『終活』
- 終活❶財産管理対策【成年後見】
- 終活❷財産管理対策【家族信託】
- 終活❸揉めさせない対策【遺産分割対策】
- 終活❹相続税対策
- 終活❺個人事業の承継対策
- 終活➏エンディングノート【無料】楽しく作る分冊型
- 終活❼楽しい家系図作成サービス
- 相続手続き・遺産整理など
- ▼知ってお得な相続知識(もくじ)▼
- 自分で相続登記手続をした方に聞きました「相続手続で苦労した理由!ベスト10」
- 相続に関与しようとする民間資格や民間団体にご注意ください。
- 最期の時が近づいたとき(葬儀前に)ご家族が確認・準備するべきこと
- 相続開始直後(葬儀後すぐ)に行なうべき手続一覧
- 相続手続トータルサポート
- 遺言寄付の受け入れトータルサポート
- 相続は早い者勝ちになりました
- 相続登記・遺贈登記の特急申請(グループ会員限定記事)
- 銀行・信託銀行の相続手続は、本当に「質の悪いブランド品」なのか?!士業の相続手続と徹底比較!
- 法定相続情報~ややこしい戸籍を読むのは司法書士が一回で十分です。銀行預金の相続手続前に司法書士にご依頼ください。
- 相続による銀行口座凍結とは?!
- 銀行預金の仮払制度(遺産分割前の預金払戻し制度)
- ▼相続財産の調査(もくじ)▼
- 相続によって引き継ぐ財産・引き継がない財産(相続の対象財産)
- 行方不明の相続預金・相続貯金の探索
- 相続で負債・借金がないかの調査方法
- 被相続人の遺品の中から、相続人や第三者名義の通帳が出てきた場合どうすれば良いのか?(いわゆる名義預金の問題)
- 相続登記や遺言の際に欠かせない不動産の近隣地調査(名寄せ)
- 相続生命保険の調査
- ▼相続人の調査(もくじ)▼
- 相続人は誰か❶基本編(法定相続人・法定相続分)
- 相続人は誰か❷数次相続・再転相続・代襲相続の区別
- 子が親より(妻が夫より)①先に死亡したとき、②同時に死亡したとき、③死亡の先後が分からないときの相続(同時存在の原則、同時死亡の推定)
- 義父母の遺産を受け取る「特別寄与料制度」
- 相続手続のための戸籍収集
- 戸籍の広域交付制度とその盲点
- あなたの戸籍謄本(住民票)が取得されましたとの通知を受けた方へ:本人通知制度
- ▼相続税申告の要否▼
- ▼遺産分割協議(もくじ)▼
- 遺産分割協議書の基礎知識、作成の流れ
- 遺産分割協議の種類と流れ
- 遺産分割協議の期間制限
- 一次相続の遺産分割協議では、二次相続のことも考えましょう。
- 相続分の譲渡・相続分の放棄
- 平成13年6月までに相続開始又は代襲原因発生の場合は注意「非嫡出子の法定相続分」
- 特別受益証明書(相続分ないことの証明書)による相続登記が流行した理由、消滅した理由から、特別受益証明書の可能性を探る
- 配偶者居住権(2020.4.1以降開始相続)
- 配偶者居住権の法的性質
- 配偶者短期居住権(2020.4.1以降開始相続)
- ▼不動産の相続手続(もくじ)▼
- 不動産の相続手続(相続登記)
- 相続登記後、売却する不動産は誰名義で相続登記したら良いですか?!
- 相続不動産売却サポート
- 何代も前の相続で、途中の相続登記を省略できる場合~数次相続で中間省略登記が認められる条件
- 相続登記に上申書が必要な場合(戸籍不足の相続登記)
- 進まない相続登記(協力しない相続人がいる場合、相続人が何十人もいる場合)の対応【調停や判決による相続登記】
- 長期相続登記未了の通知を受けた方へ/法定相続人情報
- 相続登記義務化:令和6(2024)年4月1日施行
- 所有者不明土地問題を解消するための法改正と施行時期【一覧】
- 相続した土地を国に引き取って貰う制度『相続土地国庫帰属法』令和5(2023)年4月27日施行
- ▼不動産以外の相続手続(もくじ)▼
- 銀行預金・郵便貯金の相続手続
- 上場株式・非上場株式(株券)の相続手続
- 生命保険の相続手続・税金・遺言執行
- ゴルフ会員権の相続手続
- デジタル遺産の相続手続
- 未支給年金の相続手続
- 自動車の相続手続
- ▼借金貸付金の相続手続(もくじ)▼
- 他人への貸付金(借主)に相続が発生したときの債権者の対応
- 他人への貸付金(貸主)の相続手続
- 借金の相続手続
- 相続承認・放棄の期間伸長の申立
- 相続放棄(申述)の意味と申立手続
- 相続放棄(申述)できなくなる法定単純承認とは?
- 法定単純承認となることなく、遺品を処分することは可能か?!
- 相続放棄(申述)をしても免れないことがある?!固定資産税・都市計画税のハナシ
- 相続放棄(申述)と数次相続・代襲相続
- 遺言で受けた贈与(遺贈)を放棄する方法は、遺言の書き方によって異なります。
- 限定承認の意味と方法
- ▼遺言があるときの相続(もくじ)▼
- 遺言書を探す方法(公正証書遺言、法務局保管自筆証書遺言の探索)
- 遺言検認申立
- 遺言執行者選任申立
- 遺言解釈・遺言執行
- 受遺者や受益相続人が遺言者よりも①先に死亡したとき、②同時に死亡したときの遺言・遺贈の解釈
- ▼相続に関する他の手続(もくじ)▼
- 外国(海外)在住日本人の相続手続・相続放棄手続とその必要書類(在留証明・署名証明・法定相続情報・日本公証役場)
- 日本在住外国人の相続手続
- 特別代理人選任申立(未成年者がいる場合の遺産分割協議)
- 不在者財産管理人選任申立
- 失踪宣告申立
- (民法952条の)相続財産清算人選任申立
- 特別縁故者からの相続財産の分与請求
- 他の共有者が死亡したとき、どうすれば良いのか?!~共有者の相続人への共有物分割請求~
- 相続・遺産分割のトラブル解決
- 契約書作成・精査
- 外国人の帰化
受遺者や受益相続人が遺言者よりも①先に死亡したとき、②同時に死亡したときの遺言・遺贈の解釈

相続には、大きく分けて2種類あります。すなわち、➊遺言がないときの相続と、➋遺言があるときの相続です。
この記事では、➋遺言があるときの相続において、受遺者(受益相続人)が遺言者より先に死去なさった場合に、受遺者(受益相続人)が受取人として指定されていた相続財産は、誰のものになるのか(受遺者の相続人か、本来の相続人か)について解説しています。
➊遺言がないときの相続については、記事「子が親より(妻が夫より)①先に死去したとき、②同時に死亡したとき、③死亡の先後が分からないときの相続(同時存在の原則、同時死亡の推定)」をご参照ください。
| もくじ | |
|
受遺者が遺言者より先に死亡したときの遺贈
受遺者(遺言により財産をもらう方)が、遺言者より先に死亡したときには、効力を生じません(民994Ⅰ)。
|
民法第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効) |
|
|
|
そして、遺贈が効力を生じないときには、相続人に帰属するのが原則です(民法995)。
ただし、遺言者が、その遺言に別段の意思を表示していた場合には、その意思に従う必要があります(民995ただし書き)。
| 民法第995条(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属) | |
| 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 | |
法文を杓子定規に読むと、以上のとおりの結論になります。
ただし、「別段の意思を表示したとき(民法995条ただし書き)」とは、具体的にどのような場合なのかも検討する必要があります。
この点については、後ほどご説明します。
受遺者が遺言者と同時に死亡したときの遺贈
法律用語では「以前」と「前」は、厳格に区別して使用されます。
- 以前:基準時点を含む。例えば「4月1日以前」という場合には、4月1日を含んで、それより前を意味します。
- 前:基準時点を含まず、基準点より前を表わします。
遺言者と受遺者が同時に死亡した場合については、民法994条1項を見れば、明確です。すなわち、民法994条1項は、「以前に死亡したとき」となっていますので、基準時(遺言者の死亡時点)を含みます。
よって、同時死亡の場合には、遺贈は効力を生じないことになります。
|
民法第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効) |
|
|
|
したがって、同時死亡の場合も、受遺者が遺言者よりも先に死亡した場合と全く同じ結論になります。
包括受遺者の一部が遺言者より先に死亡したとき
包括遺贈とは、個別財産ごとに受取人を指定するのではなく、包括して遺贈する場合をいいます。
下記事例で考えてみましょう。
<事例>
遺言「私は、全財産の2分の1を内縁の妻Aに、4分の1をAの長男Bに、4分の1をAの長女Cに遺贈する。」を残していました。
➊内縁の妻Aが遺言者よりも先に死亡し、➋その後、遺言者も死亡しました。遺言者の法定相続人が弟のみです(なお、内縁の妻Aも、その子BCも、遺言者の法定相続人ではありません。)。
|
┌ーーー┐
弟 遺言者ーーー内縁の妻A(1/2)➊死去 ➋死去 | 長男B(1/4) 長女C(1/4) |
<問い>
Aが、包括遺贈されていた1/2は、どうなるのでしょうか?
「長男B、長女Cに追加される」か、「弟が相続する」かのどちらかになるでしょう。
<考え方>
| 遺言書に「遺言者の死亡以前にAが死亡した場合は、Aが受けるべき1/2は、Aの相続人B及びCに遺贈する」などという表現があるか? | ||
| ▼ | ▼ | |
|
ある |
ない | |
|
▼ |
▼ | |
|
受遺者の相続人に代襲させる意思 (民995ただし書きの別段の意思)あり |
受遺者の相続人に代襲させる意思 (民995ただし書きの別段の意思)なし |
|
| ▼ | ▼ | |
|
Aが受けるべきであった遺贈1/2については、Aの子B、Cが1/4ずつ「遺贈」を受けることになる。 結局、次の割合になる。 弟:B:C=0:1/2:1/2 |
Aが受けるべきであった遺贈1/2については、弟が「相続」することになる【1】。 結局、次の割合になる。 弟:B:C=1/2:1/4:1/4 |
|
【1】包括受遺者が複数いる場合において、その一部が効力を生じないとき、又は放棄によって効力を失ったとき、受遺者が受けるべきものであったものは、「他の包括受遺者に帰属する」か、「相続人に帰属する」かという争いがありましたが、次の最高裁判決で決着しました。
|
最高裁令和5年5月19日判決(令4(受)540号、民集77巻4号1007頁) |
|
| 民法995条は、本文において、遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属すると定め、ただし書において、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従うと定めている。そして、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する(同法990条)ものの、相続人ではない。同法995条本文は、上記の受遺者が受けるべきであったものが相続人と上記受遺者以外の包括受遺者とのいずれに帰属するかが問題となる場面において、これが「相続人」に帰属する旨を定めた規定であり、その文理に照らして、包括受遺者は同条の「相続人」には含まれないと解される。そうすると、複数の包括遺贈のうちの一つがその効力を生ぜず、又は放棄によってその効力を失った場合、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き、その効力を有しない包括遺贈につき包括受遺者が受けるべきであったものは、他の包括受遺者には帰属せず、相続人に帰属すると解するのが相当である。 | |
「相続させる」旨の遺言の受益相続人が、遺言者よりも先に死亡した場合
「相続させる」旨の遺言があった場合において、受益相続人が遺言者よりも先に死亡したときに、代襲相続を認めない見解(遺言は効力を生じず法定相続が開始する)と、認める見解(受益相続人の相続人が代襲できる)が対立してきました。
私たち司法書士は、下記先例を根拠に、代襲相続を認めないとして登記実務を実践してきました。
| 昭和62年6月30日法務省民三第3411号民事局第三課長回答 | |
|
遺言が効力を生ずる前に、遺言によって相続人となるべき者が死亡したときは、遺言中に「その相続人が先に死亡したときは相続人の直系卑属に相続させる」旨の記載のない限りその部分は失効し、法定相続が開始する。 |
|
ただし、「相続させる」遺言の法的性質を「遺産分割方法の指定」と解する立場から、代襲相続を認めるという裁判例(東京高裁平成18年6月29日判タ1256号175頁)もあらわれ、現場は混乱していました。
そんな中、最高裁が判断を示しました。
| 最高裁平成23年2月22日判決(民集65巻2号699頁) | |
|
〔裁判要旨〕 被相続人の遺産の承継に関する遺言をする者は,一般に,各推定相続人との関係においては,その者と各推定相続人との身分関係及び生活関係,各推定相続人の現在及び将来の生活状況及び資産その他の経済力,特定の不動産その他の遺産についての特定の推定相続人の関わりあいの有無,程度等諸般の事情を考慮して遺言をするものである。このことは,遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定し,当該遺産が遺言者の死亡の時に直ちに相続により当該推定相続人に承継される効力を有する「相続させる」旨の遺言がされる場合であっても異なるものではなく,このような「相続させる」旨の遺言をした遺言者は,通常,遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解される。 したがって、遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはない。 |
|
民法995条ただし書きの「別段の意思」とは何か?
遺言解釈に関する最高裁判例
ここで遺言書の解釈に関する判例を復習しましょう。
| 意思表示の内容は当事者の真意を合理的に探究し、できるかぎり適法有効なものとして解釈すべきを本旨とし、遺言についてもこれと異なる解釈をとるべき理由は認められない(最判昭30.5.10民集9巻6号657頁)。 | ||
| ▼ | ||
| 遺言書の記載自体から遺言者の意思が合理的に解釈できるか? | ||
| ▼ | ||
|
できる場合 |
できない場合 |
|
| ▼ |
▼ |
|
|
遺言書に表れていない事情をもって、遺言の意思解釈の根拠とすることは許されない(最判平13.3.13)。 |
遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたっても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である(最判昭58.3.18)。 |
|
考え方
受遺者が遺言者よりも先に死亡した(同時に死亡したとき)とき、遺産を誰に承継させたいかを遺言書中に指定していないときには、「遺言書の記載自体から遺言者の意思が合理的に解釈できない場合」に該当するので、最判昭58年3月18日に従って解釈する必要があります。
いくつかの裁判例をご紹介します。
|
東京地裁平成26年5月14日判決(平24(ワ)31540号、ウエストロージャパン) |
|
|
【事案の概要】
◆Bの兄弟姉妹である原告らが、Aが夫であるBに遺産の全部を相続させる旨の自筆証書遺言が無効であるとしても、無効行為の転換により死因贈与契約として有効とみなされるべきであり、仮にそうでないとしても本件遺言書による死因贈与契約が成立し、Bの死亡により原告らが本件死因贈与契約の受遺者の地位を相続したなどと主張して、Aの孫である被告らに対し、同契約に基づき、Aの相続財産に対する共有持分権の確認等を求めた事案 ┌ー┬ー┬ー┐ 兄弟姉妹 夫B❷死去===妻A「夫に遺産の全部を相続させる」旨の遺言作成❶、❸死去 (原告) | 孫(被告) 【判決要旨】 ◆妻Aの遺言は、夫Bの妻Aに対する暴力を辞めさせるものであった。 ◆妻Aは、孫にも何とかして財産を与えたいとの意向を有していた。 ◆仮に、BとAとの間で死因贈与契約が成立したと認めることができるとしても、Aが、Bが先に死亡した場合を想定し、かかる場合であっても被告らに財産を承継させない意思を有していたとか、かかる場合には受遺者の地位をBの法定相続人に相続させる意思を有していたなどと認めることはできず、本件死因贈与契約は、受遺者とされたBが贈与者であるAより先に死亡したことによって無効となる(民法554条、994条1項)と解するのが相当である。 |
|
|
東京地裁平成28年11月17日判決(平28(ワ)13563号、ウエストロージャパン) |
|
|
【事案の概要】
◆亡Aの公正証書遺言により遺産の一部を遺贈されるはずの受遺者Eが亡Aと同時に死亡したため、亡Aの弟Xが、遺言執行者Yに対し、主位的にEに対する本件受遺分はXが相続したとしてその支払を、予備的に本件受遺分はXと他の包括受遺者が共同相続したとしてその一部支払を求めた事案 【判決要旨】 ◆亡AとEは同時死亡の推定を受けるから、本件各遺言のうちEに対する遺贈は民法994条1項により効力を生じず、遺贈が効力を生じないときは同法995条本文により受遺者が受けるべきであったものは原則相続人に帰属し、同条ただし書により遺言者が遺言に別段の意思を表示したときはその意思に従うとされているところ、❶亡AがXと対立する状況下で、❷Xの取得分に一切言及しない本件各遺言を作成したことによれば、亡Aは本件各遺言でXには一切相続させない意思を表示したと解されるから本件受遺分につきXは相続分を取得しないとして、各請求を棄却した事例 ◆遺言解釈に関する最高裁昭和58年3月18日判決を引用したうえで「原告は,本件各遺言には,包括受遺者の1人が同時死亡するなどしてその効力が生じない場合について定めた文言はないとして,原告が本件受遺分につき相続権を取得すると主張するが,かかる解釈は,本件各遺言のうち包括遺贈に関する条項のみを他から切り離してその文言を形式的に解釈したものといえ,遺言者である亡Aの真意の探究として不十分といわざるを得ないから,同主張は採用できない。」 |
|
「遺言書中に、原告に関する記載が一切の言及がないこと」を理由に、原告(受益相続人の代襲相続人)の主張を認めなかった裁判例に次のものがある。
- 熊本地裁平成16年4月19日判決、その控訴審・福岡高裁平成16年11月30日判決(ともにウエストロージャパン)
まとめ
| 本来の相続人と、受遺者の相続人が争った場合において・・・ | ||
| 別段の意思表示【なし】と判断されうる要素 | 別段の意思表示【あり】と判断されうる要素 | |
|
要 素 |
|
|
|
結 論 |
遺産は、本来の相続人に帰属する(民995本文)。 |
遺産は、受遺者の相続人に帰属する(民995ただし書き) |
別段の意思の立証は困難
別段の意思の立証は困難でしょうから・・・
受遺者(受益相続人)の代襲相続人から登記申請する場合
法務局は、関係者全員が実印を押印した上申書又は確認書(もちろん印鑑証明書添付)を要求するものと思われます。
関係者の一部がこの提出を拒否する場合には、訴訟において解決するしかありません。
相続を専門に扱う弁護士をご紹介いたします。
これから遺言書を作成する場合
例え、遺言者ご自身よりも若い受遺者、受益相続人であったとしても、万一のこともございます。
遺言書には、はっきりと予備的条項も書いておきましょう。
| 予備的条項(文言例) | |
| 遺言者は前記【氏名】が遺言者より先に若しくは遺言者と同時に死亡したとき、又は相続放棄をしたときは、遺言者は、前項の財産を前記【氏名】の長男である【氏名】(昭和年月日生)及び前記【氏名】の二男である【氏名】(昭和年月日生)に各2分の1ずつ【相続させる。/遺贈する。】 | |
一部効力を生じなかった場合の遺言執行
少し本稿のテーマから外れますが、実務上役に立ちそうな裁判例を見つけましたので、掲載しておきます。
| 東京地裁平成28年11月30日判決(平27(ワ)34310号、ウエストロージャパン) | |
|
要旨
◆亡Aの遺言執行者に選任された原告が、亡Aが平成11年4月30日にその遺産を原告外2名に遺贈する旨の自筆証書遺言(本件遺言)をしたと主張して、遺言執行者としての職務権限に基づき、証券会社である被告に対し、亡Aが被告の特定口座に保有していた投資信託受益権(本件MRF)について、遺言執行者名義の口座への移管を求めた事案において、本件においては、受遺者のうち1名が相続開始前に死亡していることから、本件遺言のうち、当該受遺者に対する遺贈に係る遺言は効力を生じないことになるが、原告は、遺言執行者として有効な部分についての遺言を執行する義務を負っているといえるところ、投資信託受益権はその性質上不可分債権であるが、遺言執行者たる原告が、本件遺言の有効部分の執行をするには、本件MRF全体の移管を求めるよりほかに方法はないから、そのようにすることが民法1012条の「遺言の執行に必要な一切の行為」として許されると判断し、請求を認容した事例 |
|