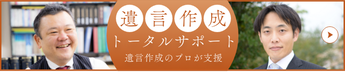新人司法書士が必ず陥る「誤字脱字などのケアレスミス地獄」からの脱出方法

ケアレスミスを連発してしまう「ケアレスミス地獄」に陥って、上長に怒られたり、自信を無くしてしまうのは、あなただけではありません。
私も、新人時代には、ケアレスミスを頻発し、なかなか直りませんでした。
このコラムは、SNSで募集した「ケアレスミスを発生させない方法/ケアレスミスをセルフチェックで見つける方法」をまとめて記事にしたものです。山本佳志先生、古田光生先生、金さん(金子孝信)先生、みー先生、ずんだ先生(順不同)、そのほか匿名希望の皆様、貴重なご意見をありがとうございます!いつも素晴らしいご意見をくださる皆様には、大変感謝しております。
| もくじ | |
|
特殊な司法書士業界(大やけどになるミス)
間違えると大やけどになってしまうのは、次のような項目です。
お客様の住所、氏名
人の名前の漢字に対して、これほど細かい業界は司法書士業界の他には存在しません。
それには理由があります。
まず、登記簿は、誰もが見ることができます。 しかも、これらは司法書士が自腹で更正登記をしたところで、間違えて登記されたという事実は残ります。
他士業の仕事の成果(判決文・和解調書、税務申告書、許認可書)は、誰もが見ることはできませんので、大きな違いです。
次に、人の名前は唯一無二のものです。
司法書士が不動産登記申請書の文字を間違えて、新築建物に登記してしまったら、それは怒られますよね。
会社登記申請書も同じです。自社の役員の名前を間違えられた、役員になってくれた方の名前を間違えられたとなれば、怒られても仕方ありません。
添付書類や議事録であっても、これらに間違いがあれば、作り直しを言われることが多いので、要注意です。
見積書の金額
手続を知らずに費用の計上漏れをした場合は、勉強不足です。勉強するしかありません。
一方、登録免許税の計算ミスや、ゼロが一つ足らない、ゼロが一つ多いなどは、失注や(クライアントとの関係性によっては)自腹負担のリスクを上げます。
官報や公告の内容
訂正公告の必要が生じますので、自腹は仕方がありません。
訂正公告で本来の手続に遅延が生じたときは、損害賠償請求も免れません。
センスが無いと思われるミス
クライアントから指摘されることは少ないかもしれませんが、気にするクライアントは「汚い書類を作りやがって」と、今後は依頼してくれないかもしれません。
そして、クライアントは、静かに去って行くものです。
次のようなミスは、センスが無いと思われてしまうので、注意しましょう。
行間の不揃い・不自然な余白
Excelで文書を作成することもあります。
文書の行間不揃いや、不自然な余白については、印刷してチェックすれば一目瞭然です。
行間にばらつきがあったり、見た目が不細工になっていないか、必ず印刷して確認しましょう。
一部だけフォント相違
ほとんどがMS明朝体で作成されているのに、MSゴシック体が混じっていれば不細工です。
こちらも印刷してチェックすれば、一目瞭然です。
ミス発生のメカニズムを知る。
本来、作成した文書を、自分でチェックしても、ミスには気付きにくいものです。まず、それを頭に叩き込んでください。
なぜなら、作成した文書は、頭の中では正しい文書であって、それに変換して読んでしまうからです。一方、作成者以外がチェックするときは、チェックする方の頭の中には正しい文書はありませんので、誤字や脱字に気付きやすくなります。
また、セルフチェックしてるつもりが、いつのまにか「読者」になってしまうという「悪い癖」がついてしまっているのです。
それでも司法書士であれば、間違いは許されません。
「自分で作って、自分でチェックしたから、間違えました」と言おうものなら、取引先を失うことになるでしょう。どんな言い訳も許されません。
ミスを絶対発生させないようにする仕組みを作るのが、司法書士の使命です。
どんな漢字があって間違えやすいのかを知る。
「どんな漢字があるか」「どんな漢字と間違えてしまうか」を予め知っておくと、ミスを発見しやすくなります。
記事「間違いやすい漢字・単語・人名集」を何度もご確認いただき、頭にたたき込んでください。
ミスしにくい方法で書類を作成する。
まずは作成段階で、ミスを減らします。
そもそも作成時点でミスがなければ、それに越したことはないからです。
コピー&ペーストで作成する。
コピー&ペーストであれば、ミスをすることがありません。
インターネットで取得した登記情報等であれば、コピーすることができます。
もっとも余計な文字や罫線|なども貼り付ける可能性もありますので、チェックは必須です。
資料とPC画面は、左右に並べて作成する。
人間の目は、上下移動よりも、左右移動の方が、得意です。
入力すべき情報が記載された資料(例えば住民票)とPC画面は、左右に並べて作成します。
左右移動が強い理由は次のとおりです。
- 視野の構造:人間の視界は、水平方向(左右)に約200度、垂直方向(上下)には上に50度、下に75度と、左右の方が広いです。
- 進化的背景:人類の祖先は地上生活をする中で、横方向に動く獲物や周囲の変化を素早く捉える必要がありました。一方で、上下方向の動きはそれほど重要ではなく、このため左右方向への感度が高まったとされています。
- 眼球運動と筋肉の働き:眼球運動を制御する筋肉は、上下移動よりも左右移動に適応しています。たとえば、外転や内転時には特定の筋肉が効率的に働きますが、垂直方向の運動にはより多くの筋肉や神経の協調が必要となり、複雑な制御が求められます。
- 記憶力との関連:研究によれば、目を左右に動かすことで脳全体が活性化し記憶力が向上するという結果も示されています。このことからも、人間は左右方向への眼球運動において優れた能力を持つことが示唆されます。
ミスを発見しやすいチェック方法を実行する。
自分は必ずミスしていると思ってチェックする。
人間は必ずミスをする生き物です。
自分も必ずミスをしていると思ってチェックする必要があります。
精神論は沢山挙げても仕方ありませんので、以降は具体的な方法をお伝えします。
時間を空けてチェックする(別の事件処理を挟む)。
脳をリフレッシュした状態でチェックするためです。
また、休憩や別の事件処理をしている間に、チェックすべき項目や論点などを思いつくこともあります。
頭が一番すっきりしているときにチェックする。
こちらも上と同じで、クリアな脳でチェックするためです。
作成当日ではなく、翌日チェックすることで、自宅で休憩中に、チェックすべき項目や論点などを思いつくこともあります。
Wordのアラートは必ずチェックする。
Wordには、アラート機能が実装されています。印刷する前に、アラートが表示されていないかチェックします。アラートはクリックすると、アラートが出ている意味が表示されますので、下表を覚える必要はありません。
ただし、印刷してチェックを依頼する場合には、チェックする方も気付きにくいので、要注意です。チェック担当者においても、デジタルデータをもチェックする習慣をつけると良いです。
| 色と種類 | 意味 |
| 赤い波線 | スペルミス、Wordの辞書にない単語を指摘する。 |
| 青い波線(二重線) |
文法エラー、表記ゆれを指摘する。 例:「データ」と「データー」 |
| 緑の波線 |
文法的な誤りを指摘する。 例:×食べれる(正しくは「食べられる」) |
印刷して紙でチェックする。
パソコン画面上でチェックするよりも、印刷して紙でチェックした方が、ミスを発見しやすいです。
- エラー検出率の高さ:多くの研究が、紙での校正が画面上での校正よりもエラー検出率が高いことを示しています。例えば、紙では液晶ディスプレイよりも30%以上多くエラーを発見できたという結果があります。
- 視認性と集中力:紙は反射光を利用するため、目に優しく、長時間の作業でも集中力を維持しやすいとされています。一方、液晶ディスプレイは透過光を使用しており、目の疲労や注意散漫を引き起こしやすい傾向があります。
- 文脈的な誤りへの対応:文脈的な誤り(前後関係を理解しないと気づけないようなミス)についても、紙での校正が有利であることが確認されています。
左右に並べてチェックする。
これは、作成する際と同じです。
人間の目は、上下移動よりも、左右移動の方が、得意だからです。
漢字は指を動かして書いてチェックする。
漢字は、実際に指を動かして書いてみて、細かな違いを意識しながらチェックする。
漢字を部首などに分解して声に出して読んでチェックする。
漢字を部首などに分解して声に出して読む。
音読みなら訓読み、訓読みなら音読みに変換しながら一文字ごとに切って読む。
- 佑なら「にんべんにみぎ」とか。
- 平家建なら「へいけだて」とか「ひらいえだて」とか。
- 会社の目的であれば、「工業」は「えこうぎょう」とか、「興業」は「おこすぎょう」とか。
音読はミスを減らせます。目で追うだけだと脳の高度な補完機能が自動的に働いてしまう結果、誤りを見落とします。読み方を変えて音読することで、補完機能を強制オフにして処理スピードをわざと落とすことで、誤字脱字を発見しやすくします。
一文字ずつ消しながらチェックする。
鉛筆で一文字ずつチェックマークをつけながら、チェックする司法書士も多いです。
文字の下に「✔」をつけていくかは人それぞれです。
修正した書類は、もう一度印刷してチェックする。
修正したことによって、他の箇所との齟齬が生じることがあるからです。
× 何度もチェックする。
私が提案した方法ですが、同職の皆様には却下されました。
私自身も、同じ書類を何度もチェックすることはありません。ただし、修正した書類はもう一度印刷したうえで、セルフチェックすべきことは、上で述べたとおりです。
事務所全体でミスを無くす。
ミスをして、自腹や損害賠償が発生するよりも、取引先を失うよりも、事務所全体でミスを無くしましょう。
複数人でチェックする。
作成者以外の方がチェックすることで、作成者本人が気づけなかったミスが見つかることは多々あります。躊躇せずチェックを依頼しましょう。
上長がいないときは、同僚や部下にチェックを依頼する。
上長がいないときには、同僚や部下にもチェックを依頼します。
ミスを完全にゼロにするための対策ですので、恥ずかしいなどと思う必要は一切ありません。
堂々とチェックを依頼しましょう。
万一のため適切な金額の司賠責保険に加入する。
どれだけ工夫をしても、何年何十年かに一回は、手痛いミスをしてしまうこともあろうかと思います。そんなときに、顧客に適切な賠償金支払いができるようにしておく必要があります。司法書士賠償責任保険の上乗せ保険にも加入し、適切な金額の上乗せ保険料を支払いましょう。
司賠責保険の保険料がそれほど高額ではないのは、司法書士全員が苦労してケアレスミス(保険事故)を防いできた結果だと思います。
ケアレスミス地獄に陥った皆様が、この記事を読み、すぐに実践して、一刻も早くケアレスミス地獄から脱出できることを祈念いたしております。